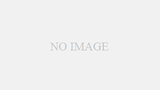「もう、会えないの……?」
この言葉は、愛犬「ミミ」が亡くなった日の夜、8歳の娘・紗季がぽつんと漏らしたひとことでした。ペットとの別れは誰にとってもつらいものですが、小さな子どもにとっては「死」そのものを初めて体感する大きな出来事です。今回は、実際に娘が体験したペットロスと、その回復までの道のりについて記録として綴ります。
家族の一員だった「ミミ」
ミミは、私たち家族が飼っていたトイプードルで、紗季がまだ2歳だったころから一緒に暮らしていました。ミミはまるで姉妹のような存在で、毎朝一緒に起きて、一緒に遊び、一緒に眠る。そんな日々が6年間続いていたのです。
しかしある日、ミミは突然倒れ、そのまま二度と目を覚ましませんでした。あまりにも突然の出来事に、私たち大人でさえ心の整理がつかず、どうやって娘に伝えればいいのか悩みました。
ミミの死と、娘の反応
最初に知らせたとき、紗季は信じられないという表情をしていました。翌日、火葬の準備をする中で、彼女はやっと現実を受け入れはじめたようで、「ごめんね」「大好きだよ」と何度も何度もミミの体を撫でていました。
火葬のあとはしばらく、「学校に行きたくない」「またミミに会える?」と、情緒が不安定な日が続きました。
子どもの心に起きた“変化”
ペットロスによって、紗季は少しずつ変わりました。
- 以前より感情を言葉にすることが増えた
- 一人でいる時間を好むようになった
- 夜に「ミミの夢が見たい」と泣くことも
このとき私たち親が心がけたのは、「無理に元気づけない」ことでした。代わりに、娘の気持ちを肯定し、時間が解決することを信じて寄り添うようにしました。
回復へのきっかけ
ある日、学校の図書室で見つけたという「虹の橋」の絵本を読んで帰ってきた娘は、こう言いました。
「ミミ、向こうで元気にしてるんだよね。会える日が来るんだよね」
その日から、紗季はミミの写真にお花を飾ったり、手紙を書いたりするようになりました。自分なりの「供養の形」を見つけることで、少しずつ気持ちを前向きに持てるようになっていったのです。
親として気づいたこと
子どもは、想像以上に深く傷つきます。そして同時に、大人が思っている以上に、ちゃんと乗り越えていく力を持っていることも実感しました。
親として私たちができるのは、
- 悲しみを否定せずに受け止めること
- 無理に「忘れよう」と言わないこと
- 話したいときに、ちゃんと話を聴くこと
そして、子どもが自分のペースで「大切なものを失った痛み」と向き合うための環境を、そっと支えることなのだと感じました。
まとめ:別れがくれた“強さ”と“やさしさ”
ミミとの別れは、私たち家族にとってかけがえのない痛みでした。とくに娘にとっては、「死」や「永遠の別れ」を学ぶ人生で初めての大きな経験だったと思います。
しかしその経験を通じて、紗季は命の尊さ・愛情の深さ・悲しみを越える力を、自分の中に育ててくれました。
もし今、ペットロスに苦しむ小さなお子さんがいるなら、ぜひ「泣いてもいい」「悲しんでいい」と伝えてあげてください。そして、その先には必ず“心が癒える瞬間”があるということを、そっと信じて見守ってあげてほしいと思います。
まとめたページもご用意しています。ぜひご覧ください。
子どもと向き合うペットロス